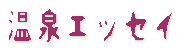| 序 |
信州に最後に残された秘境、それが北信濃の最奥にある栄村、秋山郷である。
平家の落ち武者の隠れ里と呼ばれ、世間から取り残された地域である。谷に沿っていくつかの集落があるが、あまりにも生活するのに厳しい環境故に、いくつもの村が絶滅するなど、苦しい生活を続けてきた。
現在でも、日本有数の豪雪地帯であるために、大雪の年には道路(ルートとしては殆ど1本しかない)が寸断されるなどの災害に遭っている。
|
|
 |
この秋山郷を世間に最初に紹介したのが、鈴木牧之と言われている。
鈴木牧之は新潟県魚沼郡塩沢町の生まれだが、文政年間(1828年)、58歳の時に秋山郷を訪れ、「秋山記行」という紀行文を記した。死後に写本で出回り(出版はされなかったらしい)、秋山郷の存在がそれなりに世間に知られるようになったと言われる。
この秋山記行は、民俗学の走りなどと評している人もいるようであるが、私が読んだところでは、どう読んでも面白紀行文である。作者本人はいたって真面目に「事実」を正確に記そうとしているのかもしれないが、今読むと、必死に(何度も絶滅の危機に遭いながら)生活する秋山郷の住民を一見小馬鹿にするかのような酷い記載に満ちており、シュール極まりない。
ところが、現在の秋山郷においては、鈴木牧之はヒーローとして胸像まで建てられている存在になっている。これも秋山郷の人たちの人の良さと、度量の大きさを表しているともいえるだろう。
|
|
 |
主人公は鈴木牧之本人。道先案内人である桶屋の団蔵とともに訪れる。
これから、鈴木牧之とともに、秋山郷を旅してみよう。
|
|
|
| 見玉 |
鈴木牧之は塩沢町の自宅を出て、秋山郷に向かう。
1日目の宿は見玉不動尊の正法院。
「飯もうまく、味噌汁も鰹のだしを沢山使っている様子でうまい」
と食事も楽しんでいる。村長達を呼び寄せて話を聞くなど、ご機嫌な夜を過ごしている。深夜にまで及んだ話が終わり、村人達は帰って行った。
しかし、寒くてこの夜はほとんど眠れていない。牧之は、ここから秋山郷での旅の最中、殆ど眠れないというかわいそうな状況が続く。
目覚めて朝食を取るが、
「夕べの茄子の温めた汁と、お菜も夕べの茄子漬。昨日は空き腹であのようにうまかった汁も、冷飯も、茄子漬までもが苦くてたまらない。そこであらかじめ用意して持ってきた梅干、胡麻、味噌を出して食べた。」
いよいよ毒舌が始まる。
「桶屋は、寺の奥さんがあまりに美しいので、びっくりして見とれていた。」
文脈と関係なく女性の話が混じるのが、鈴木牧之の文章の特徴である。
|
|
 |
| 清水川原 |
見玉不動尊を出発し、秋山郷にいよいよ入る。
最初の村は「清水川原」。定助という人の家でお茶をもらう。この時はお茶への文句は言っていない。
お茶代としてありあわせの短冊に5,6枚字を書いて渡している。村人はこれを読めないため、「その書いた字を何度も何度も読んでくれと言うので、読んで聞かせ、ここを立ち去った」。
現在でいうサインみたいなものだろうか?
|
|
 |
| 三倉 |
次の村は「三倉(見倉)」。桃源郷に迷い込んだような、と評している。
ここでまたお茶を頼み、持ってきた焼飯をお茶漬けにして昼食としている。
食事が終わって、
「私も秋山の流儀で、土足のままで、ひどく破れて汚れた筵の上に寝転んで眺めていると、老婆のぼさぼさに髪が乱れているのと、粗末な着物がいかにもぼろぼろなのと、その嫁らしい女の髪もぼさぼさで、櫛など使っていない様子が目に付いた」
・・お茶をごちそうになっておいて、ここまで酷く言う必要はないと思うのだが。
|
|
 |
| 中ノ平 |
続いて「中ノ平」村へ。
「ここも気の毒にたった二軒」。
家に寄ると、嫁と姑らしい女性2人がいた。
「またしても男という男は、秋の仕事の忙しさで家にはいない。これでは何も質問することができない。言葉が通じない外国に一人で行っている気分である。」
女性への差別意識は時代的に隠れようもないが、ちょっとは訊いてみればいいのに、最初から何か諦めムードである。
ここで「出がらしの真っ黒なお茶」を出してもらっている。
「出がらし」とか、書かなくてもいいのに。
またサインを残して家を出る。
|
|
|
| 大赤沢 |
次の「大赤沢」村まで厳しい道を歩き、到着する。
村長らしい老人、藤左衛門に話を聞く。
その聞く体勢が面白い。
「土足は筵の方にして畳の上へ寝転んで耳を傾けた。」
人にものを聞く体勢じゃないような気がするのだが。
牧之は、村に源氏の氏神である八幡宮があることを知り、平家の一族としてはおかしいのではないかと突っ込むと(ここら辺の意識はさすがである)、大赤沢だけは平家ではないと言われる。
牧之と藤左衛門は大いに語り合う。
老人は言う。
「食べ物など、若いときとは違って皆ぜいたくになった。昔は栃や楢の実を沢山食べた。今では粟や稗を多く食べる家が出てきた。こんなぜいたくがひどくなってはいけない。これは困ったことです。」
この老人は粟や稗を食べる「ぜいたく」を嘆いているのだ。この老人が今の日本を見たら、どのような感想を漏らすだろうか。
|
|
 |
| 甘酒 |
大赤沢は越後と信濃の国境付近の越後側にある。ここから少し行ったところに「甘酒」という村がある。ここも2軒だけの村。
女性が一人いる。
「その美しさは、世間並み。髪には油もつけないので赤黒く、首筋までばらばら、それを無造作に束ねている。手足が丸出しの短い着物をまとい、ほつれた帯を前で結んでいる。」
牧之の女性の描写は何とかならないのか。
「ぼろぼろの筵の上で、例によって茶袋を取り出そうとする。」
親切にお茶を出してあげようとしているのを「例によって」と。
一言よけいなのが牧之の文章の特徴である。
女は語る。
「昔からこの村の人数は増えもしなければ、減りもしません。すべての秋山全体で一番最初の村でした大秋山という村がありました。川の西に八軒の村でしたが、四十六年前の大凶作で皆飢え死にしてしまい、今では一軒も残っておりません。それにくらべて、私の村はいつも二軒だけ、大凶作も、せつない思いはいたしましたが、とにかく生き延びることができました。今では楽に食料を手にすることができるようになりました。」
・・この時から10年後、この村は飢饉で滅ぶ。今は跡形もない。
|
|
 |
| 小赤沢 |
すぐに「小赤沢」村に付く。
ここから信濃国に入る。今は小赤沢温泉ができて人気であるが、当時は入浴するということはなかったと思われる。
もっとも小赤沢という名前が付いているから、茶色い鉱泉の存在は昔からあったのだろう。ただ、秋山記行には登場しない。
牧之はここで宿泊することにする。といっても、宿があるわけでもなく、強引に頼み込むのである。
頼む立場であるにもかかわらず、
「今夜こそ暖かい夜具にくるまりたいものと、ひたすら思えてならない。」
などと偉そうなことを書いている。
結局「里と同じような蒲団を持っている」「好都合な」福原市右衛門という村人に頼み込むことにする。
頼むと、市右衛門は
「私の家には米がございません。粟飯と茸汁でも良いのなら。」と言う。
これに対し、牧之は
「私どもは、米も、味噌も、野菜も持ってきました。宿さえ貸してくださればけっこうです」と答える。
貧しい村人にとって特別のごちそうであろう、米も味噌も持ってきた、とか自慢げに余計なことを言わなくてもいいのに。
|
|
 |
中に入ってじろじろといろいろなものを観察する。観察するために旅をしているのだから、これはいいだろう。
問題は女性を観察して評価するときの表現である。
「この家に婦人が三人いた。つくづくと婦人達の姿を観察すると、髪は結っているが、油はつけていない。なんとも裾の短いぼろ着を着、あるいはその上に網衣という袖なしを着ている。それだけではない。帯らしいほころんだものをまとっている。
宮殿の中で育った王の后でも醜い顔の人もいよう。逆に乞食の中に生まれ育っても、すばらしい美人がいるものだとの諺のとおり、二人の婦人は、里でも稀な美しい顔立ちである。また一人は、肥え太っているのでおたふく顔、これも美しい。」
美しい女性を見て感嘆しているようである。
「古い歌のように、「植えてごらんなさい。花が育たない里はない。心次第で身はいかに賎しくとも・・」と胸中で歌っている」
身が賎しいとか、一言多いのである。
|
|
 |
夕食を食べる。料理を家の人にしてもらうが、
「持参の白米は、焚いてもらわなければよかったのに、できばえはくじゃくじゃで、私は歯がないといっても、これでは粥である。それを縁が欠け、塗りもはげた赤い椀に盛り上げ、白木の大きな栃の折りたたみの膳に乗せて食べた。」
普段粟や稗ですら贅沢と言われている村で、いきなり白米を料理させて自分だけ食べ、その料理法に文句をつけている。
「宿のおかずだといって、汁椀に里芋、大根を細かにし、味噌汁で煮たものを出してくれた。それを味わうと、里芋・大根の下に、2,3センチの厚さで小判の形の堅い灰色のものが入っている。これはきっと秋山の粟餅なのだろうと一口食べてみたが、そのまずいことまずいことといったらない。のどを通らない。一方、宿の男女はと見ると、いかにもうまそうに、口に含んで味わっている」
せっかく出してくれたものを、そんなにまずいまずい言わなくてもいいのに・・。
「私は小便に立とうと灯りを頼むと、例の松明を灯して、家の者が案内してくれる。草履とか下駄のようなものは見あたらない。ともかく路地を身巡らすうちに、古い草履を一足探してきてくれたので、この草履を使った。この辺りが開けていない事情が思われた。便所へ行くときも、きっと裸足なのであろう。いつも足を洗わない生活のためなのだろう。」
どうにも村人を馬鹿にしているような感じがしてならない。
「もっとも、私は青空の下で用を足してしまったので、この家の便所の様子は分からなかった。」
あれだけ草履を探させておいて、便所まで行かずにそこら辺で用を足している。人の家なのに。何とも失礼な人である。
|
|
 |
その後、牧之は老人と大いに語り合い、秋山郷の食生活や風俗などについて聞き取る。
老人は言う。
「ここには盗人は全くおりません。家へ盗人が押し入った話などございません。畑の作物を取られたということもございません。ばくちも、酒も、道楽もありません。また、庄屋殿への土地所有の争いごともございません。ただ夜も昼も仕事をするだけの土地でございます。」
これを聞いて、牧之は、
「源平の合戦の話が伝承されている様子もなく、いささかの争いごともなく、本当に満ち足りた賢者の村だと言うべき地である」
と感心している。
確かに秋山郷は人のいい人が多い。それにしても、秋山郷に入って初めて褒めたような気がする。
話も終わり、いよいよ寝ようとするが、蒲団のあまりのみすぼらしさに、牧之はまたぼやき始める。
「ああ、この家が二十八軒の中でいちばん豊であり、それにふさわしい蒲団だったのかと思うと、おかしくもあり、また悲しくもなる。これではゆっくりくつろごうにもくつろげない。帯を解かないのでくたびれも治らない。」
「時節は晩秋の長い夜、しかし、とても夢を見るゆとりもない。頭も寒いので、頭巾を目深に、それも二枚重ねにしてかぶった。それでもはげ頭は寒くてたまらない。」
「私は鶏の鳴く朝の訪れをひたすら待った。蚤はしきりに身体のあちこちをさして、かゆくてたまらない。樫の木の枕も固くて泣きたくなる。」
結局一睡もできなかった様子である。
|
|
 |
この小赤沢で牧之が見たがって懇請したものが2つある。
1つは家系図である。これは、昔から開けてみることはならないということになっており、本家である福原平右衛門の家のてっぺんに結びつけてあるとのことであり、見せてもらえなかった。
ちなみに、この系図は、現代のその末裔の人に聞いたところ、「先年家を直したとき、屋根裏の垂木に煤だらけの固まりが結びつけられていました。それが大事な系図だとは知らなんだので燃やしてしまいました」とのことである。ちょっとうっかりとしか言いようがない。秋山郷の人たちも「秋山記行」を色々と宣伝しているが、そのわりに、しっかり読み込んでいるのかはよく分からない。
もう1つ、牧之が見たがったのが、黒駒太子の掛け軸である。
山田助三郎という人が持っており、何度も頼み込んで家まで行ったけれど、盆と正月にしか開帳しないと言うことで見せてもらえなかった。
何とか自分の気持ちに整理をつけるが、その勢いで今度は見てもいない絵にけちをつけ始める。
「地は絵絹に書いたのならば、よくある物で、特に見なくともよいと。考えるに、この主人が私に見せまいとしているらしい、そのわけは、絵絹とは雪舟や元信時代まで古くはあるまい。
この絵を目利きが見れば、きっとそれを見破るに違いない。そこで物事をよく知っていそうな人には絶対に見せないことに村中で決めているのではないか。
この絵像の祟りとして、例の秋山育ちの正直一途から、それを真に受けて、秋山の人だけで、決して他の人には見せてはならないと決めているのだろう。」
何ともけちょんけちょんな言いぐさである。
|
|
 |
| 上野原 |
小赤沢を出立し、「上の原」へ向かう。
「上の原」には、家が十三軒ある。
現在上の原には「のよさの里・牧之の宿」として、牧之が泊まった宿を再現したという宿がある。
このように秋山郷では牧之はヒーロー扱いなのである。上の原温泉には露天風呂があり、鳥甲山を仰ぐことができる。なかなかの絶景であり、人気がある。
実際は上の原には牧之は泊まっていない。
ただ、一軒の家には寄ってお茶を頼んでいる。
「鉄製の薬罐から出がらしの渋茶を、茶碗にこぼれるほど一杯に注いで、大きな白木の盆にのせて出してくれた。」
相変わらず「出がらしの渋茶」とか、表現が酷い。
御礼に相変わらずのサイン、短冊を書いてあげる。
しかし、「これは何という物か、読んで下さい」と言われる。字が読めない人が多いのだ。
これに対する評価が酷い。
「「それにしても、この秋山には梅の木は一本もないそうですが。」昨晩、小赤沢での話では、春は鶯も沢山鳴くけれど、鶯だけで梅がない村では風雅というものがない。特に、この小赤沢・上の原・和山・屋敷の村々は、平家の子孫と聞く。文字ぐらいは読めても良さそうなのだが。
里では天神様を祭る。梅が庭にない家では梅の花の枝をもらってきて祭る。この神は読み書きの神様なので、そのご意向も和歌で示される。その歌は、「ここに梅があったならば、こんな賎しい粗末な家へでも天神様はお立ち寄りになり文字を教えられよう。」と。梅の木を植えてこの神を祭ったなら、こんな短冊の文字も読めるようになると教える。」
賎しい粗末な家とか、お茶をごちそうしたばっかりにこんなことを言われて悲しすぎる。
村人も、
「梅は、里よりも三、四倍も寒い土地なので、育ちません。」
と悲しげに答えるが、残念ながら牧之が意に介した風はない。
|
|
 |
| 和山 |
この次は「和山」である。
今は和山温泉があり、いくつかの民宿が点在している。といっても、仁成館を初めとしていくつも休業してしまい、なかなか厳しい環境ではある。
牧之が旅した当時はもっと寂れていたらしい。
「わずかに五、六軒で、それも家がまばらに散在し、二軒並んで隣り合わせというのはない。」
牧之はここの家を借りて昼食を取る。
「桶屋が、「今日はどうして蕪の雑炊はしないのか」と聞いた。」
この桶屋もなかなか無礼な男である。
村人たちは蕪の雑炊ではなく焼き餅を食べていた。
「その大きさは、私たちの家で食べる餡の焼き餅を四つぐらいも合わせたほどの大きさ。それを二つに割ってむしゃむしゃと食べる姿は、鬼女みたいである。」
いくら何でも村人を捕まえて「鬼女」はないだろう。
出されたお茶に対し、
「私たちは、焼き飯をたき火にのせ、木切れを火箸として火をかき寄せて温める。その内に出がらしの茶も湧いて、大きな品のない、汚れた茶碗に入れて出してくれた。それは、すすのように黒い色をし、木の皮でも煎じたような変な味で、とても一口ものどへ通りそうにない。」
と、表現はさらに酷くなっていく。
「吐き出すわけにもいかず、やっとの思い出一口だけ飲み込み、こんなに長旅で疲れては、茶を飲むと疝気に悪いと嘘を言って、私だけはお湯を沸かしてもらう。焼き飯をこのお湯で粥のようにし、持参してきたおかずを取り出して食べた。」
まあ、ある意味正直な人ではある。
一応吐き出さなかっただけよしとしようか。
|
|
 |
牧之が家の中を見渡すと、30歳くらいのご婦人がいるのに気づく。
「人目を全く気にしていない暮らしぶりで、幽霊みたいに乱れた髪を頭の上で丸めて結んでいる。着物は長さが十分でなく、手も足も丸出しである。」
と、身なりの表現は相変わらず酷いが、
「こんな破れた着物を着ているのだが、その顔立ちは実に美しい。鼻はちょうどよいほどに高く、目は細い。三日月のようなしとやかな眉、顔色は少々黒いと思うが、おはぐろをつけない歯は雪よりも白く、こんな美人を見たら誰でも心ひかれるに違いないであろう。」
牧之53歳は人妻に恋をしてしまったようである。
「これは泥の中に咲いている蓮の花のようであり、雨に濡れそぼつ芍薬といった風情である。」
「こんな深山幽谷の中、虎や狼、狐の住むところと思われるごく貧しい家に育ちながら、こんな美しい人がいるとは気の毒の限りではないだろうか。」
・・あまりに人妻を褒めるあまりに、周りを悪く言いすぎである。牧之は敵を作るタイプだと思われる。
さらに、もう一人の女性を見つける。
「もう一人の若い婦人は、太っている。太いひょうたんのような足を囲炉裏に投げ出している。この人もまた手足丸出しの着物に、ぼさぼさの髪、油もつけていない。平家の子孫とならば、これは鳥坂山落城の時の有名な醜い大女、焚額女の血筋なのだろうか。鼻筋は低いし頬高だし、これ以上具体的には書かずにおく。」
もう充分具体的に書いていると思うが。本当に敵が多そうだ。
家の老人が語る。
「平家の子孫が住んでいたという、川の向こうの大秋山は、天保の飢饉で皆飢え死にしてしまい、八軒ともなくなって、今は跡形もありません。けれども、この大秋山と私の村とは、秋山の発祥の地です。昔はこの村も二十二軒、また、この村はずれの高い上の台にも、家が二十一軒もあった大きな村でしたが、四十六年前に皆死に絶えてしまいまして、今ではたった五軒だけになってしまいました。」
悲しい話である。
|
|
 |
和山温泉には2回泊まったことがあるが、その2軒とも今は民宿・旅館を廃業してしまった(和山荘・仁成館)。経営者が高齢のためと修理のお金が出せず直せないためであるが、本当に残念な話である。200年の時を超えてまた危機を迎えているのであろうか。
秋山記行にも和山温泉は登場する。
「また、質問する。この村の外れの、中津川の辺りに温泉があるか。」と。「ここから四、五百メートル行くとあります。湯は澄んでいて熱い。」と言う。しかし、その温泉へ酔っていると、湯元の村まで行くには時間が足りなくなるので、その温泉を見れないのは残念でならない。」
再度美人の婦人が相当気になったらしくて、声をかけている。
「秋山は広いといっても、あなたほどの美人は他にはいません。こんな深い山の育ちの家とはいいながら、錦や綾を着て、真珠の簪でもさし、白粉で化粧したら、あなたなら殿様の奥方になられても恥ずかしくはありません。」
ほとんどナンパである。改めてもう一人の若いご婦人が気の毒でならない。
例によって短冊5,6枚を書いておいて出発する。
|
|
 |
| 湯本 |
和山から険しい道を越え、湯本(現在の切明)に至る。
「蝦蟇仙人や鉄櫂仙人の住み家かと思われ、とてもその景色の素晴らしさは言い尽くせない。こうして夢の中で仙人の世界にはいるという気分になり、とても人間世界のこととは思われない。」
ようやく牧之も新しい境地に達しようとしているようである。
「遙か向こうが、急に幕が開いたように大樹海が切れると、川の向こうに湯本の家々が見えてきた。とても嬉しく、夕日が西へ傾く中に、山々の紅葉が、なるほど平家の数万旗の掲げる赤旗が立ち並んでいるといった光景である。」
「こんな素晴らしい地を、箱や袋の中へ納めておきたいような気持ちがしてならない。」
|
|
 |
こうして、牧之はようやく切明に到着した。
宿に泊まり、まずは温泉に入っている。
「まことに人の全くいない別世界で、命の洗濯をしているような気持ちだった。」
「人間、五十、七十まで生きられる人は稀である。私も太陽が西の山へ沈もうとする年齢になった。この入浴だって、これがこの世で最後、明日は死が迎えに来るかもしれないと思い、長い間、湯につかって時を過ごした。」
と悟っている。
この気持ちはなんとなく分かる。私もまだ太陽は頭の上にある年齢であると思うが、一つ一つを大事にしたいとは思う。
|
|
 |
牧之が訪れたのは開湯して20年くらい経った頃らしい。今は秘湯ブームもあって、手堀ができる河原の野湯が有名になっている。スコップを片手に訪れる人が後をたたない。素晴らしい風情である。雄川閣など3軒の宿がある。
牧之は相変わらず眠れていない。夜明けと共に温泉に行き、
「大寒地獄から急に極楽へ行くと、こんな気分になるのだろうか」
と漏らしている。
「念仏を数百回、先祖代々の御戒名を唱えていると、やがて空の星は次第次第に見えなくなり、湯殿の仮の柱の辺に脱いでおいた衣類は、しばらくの間なのに、もう霜が上に降りていた。」
牧之は切明に2泊して、雑魚川を散策し、紅葉の絶景に感嘆したりしている。
夜には狩人2人と大いに語り合っている。今もまたぎはここら辺で働いているというが、我々には想像も付かない生活であろう。牧之は狩人から最近とれたという猿の皮を購入した。
|
|
 |
2泊目も殆ど眠れず、朝になる。
「親子3人に、ぜひとも再びゆっくり湯治に来たい、とあいさつした。
しかし、心の中では、「平均寿命を過ぎた年齢でもあり、こんな山奥へもう一度やってくる機会など思いもよらない。さすがにこの湯はこの世での見納めか。」と、しきりに人生の寂しさを感じ取った。」
これまでと違い、ちょっと寂しく切明を出立する。
|
|
|
| 屋敷 |
ここからは中津川の西側を下っていく。まずは「屋敷」村がある。
牧之が旅した当時は十九軒ほどの村であった。屋敷温泉が現在もあり、2軒の温泉宿(秀清館・かじか荘)がある。
川のすぐ脇にあり、激流になると水没の危険もあるのではないだろうか。一段低いところに露天風呂がある。道を通る人から丸見えで、昼間に入るのには勇気がいるだろう。硫黄臭漂う薄い白色のお湯で、体への泡付きもある。素晴らしいお湯である。
牧之が旅したときには温泉は発見されていないようである。弘法大師ゆかりの温泉でもあるので、もっと詳しく村人に話を聞いていれば、出てきていたかもしれない。
|
|
 |
| 大秋山 |
「屋敷」の後は「大秋山」であるが、牧之が旅した時には既に大凶作で皆飢え死にしてしまい、絶滅していた。
「今は家が一軒もなく、果てしない茅原となり、平家代々の隠れ家も、この晩秋の最中、きりぎりすが数限りなく集まって鳴いているだけである。しかも、畦道の稲刈り時にいなごが群がるように、草鞋の踏み場所がないぐらい飛んでいる。
これは平家の落人の魂ではないかと思う。しきりに昔のことが偲ばれた。」とある。
ここは今も残っていて石造物がたくさん立てられている。
林の中で独特な雰囲気があり、何とも言えない空気が流れる。見える人が見ると何か別なものが見えるかもしれない。
|
|
|
| 上結東 |
次は「前倉」。前倉橋の絶景を見た後、「前倉」村の家で食事をする。
この日は「上結東」の太右衛門邸に泊まっている。
老人と大いに語り合い、情報を聞く。牧之は切明を出てから、妙に毒舌が少なくなっている。切明で何か人生観が変わったのであろうか。
寝るときも、「さて寝ようとすると、蒲団がないことは言うまでもない。」と諦観したように書きつづっている。
「湯本で例の狩人から買った猿の皮を敷き、道中蒲団に合羽までを掛け、真ん丸になって休んだが、全然眠れない。秋山での苦しみはこれだと思う。そのうちに蚤が体中をさしてかゆくてたまらない。これは猿の皮のせいだと、そっと取り出して捨てた。夜中過ぎ、疲れて眠ってしまった。」
さりげなく買ったばかりの猿の皮を捨てているのはご愛敬。
結東には現在は立派な温泉入浴施設(萌木の里)が作られている。露天風呂から眺められる山風景が素晴らしい。人家が全く見えない。
|
|
 |
| 逆巻 |
朝、出立して、「逆巻」という村に到着する。
四軒しかない村であるが、土蔵もあり、牧之も感心している。
猿飛橋という橋があり、それをわざわざ見に行き渡っている。改めて物好きな人である。
「いつもの通り、腹ばいになって中程まで進む。橋はしきりに振動している。冷や汗が流れて顔も濡れ、やっとの思いで向こう岸の大岩へ辿り着いた。」
猿飛橋をしばし眺めてその絶景に感動し、この地を後にしている。
逆巻には今、一軒宿の温泉宿川津屋があり、洞窟風呂が売り物である。
宿のすぐ近くに猿飛橋があり、牧之も眺めた風景が、変わらず今も眺められる。
ここが秋山郷の入り口でもあり、出口でもある。ここで、牧之の短くも長い秋山郷旅行は終わりを告げる。
|
|
 |
| 結 |
最後に牧之は、こうまとめている。
「秋山は全くの別世界、古い硯のようなものだと思った。」
「よくよく考えてみると、我々文明の中で暮らす里の者は、さまざまな悩みを身心にため、欲望をほしいままにし、鳥や魚の肉を食べ散らし、悩みや悲しみで心を迷わして、日々暮らしているのではないか。これでは夏の虫が火に入り、流れの魚が思わず餌にかかるように寿命を縮めるばかりである。少しでも暇を手にすると、私のように金銭欲や名誉欲に走り、十返舎一九の著述を助けようとしてこの国境を旅するのも、皆命を縮め、寿命を削ることだと悟らなければならないのに、悟れない。」
「ここ秋山の人こそ神のように長寿である。これは自然のままに生活し、栃の実や楢の実、粟や稗などを常食にしている。これは天から授かったこの土地の産物である。その生活ぶりも仙人のように、つつましく暮らして飲酒もしない。正直一途で、夜戸締まりもしないとは、昔の聖代のおもかげも感じられる。年貢もほんの少しで住むという。手足が動く間は、山の畑で働き、雨露も、風霜もものともしない。全く鳥や動物と同じ、自然のままの暮らしだといえる。」
「できることなら、この私も一度はこの秋山の猿飛橋の絶景に庵を作り、中津川の清流で命の洗濯をしたいものだと思うようになった次第である。」
|
|
 |
|
ここ秋山郷は、鈴木牧之が訪れてから180年が経過している。
牧之が訪れて数年後に全滅した村もあるし、生き延びた村もある。
180年前の当時から比べても、人口はせいぜい数倍にしかなっていないだろう。変わったのは電気が引かれて、1本の舗装道路ができたこと、牧之の力もあって(多分)少ないながらも観光客が訪れるようになったことくらい。
新緑の季節、紅葉の季節。
私が交通の便がいいとはとても言えない、この秋山郷に引き寄せられるように何度も足を運んでしまうのは、まさに「命の洗濯」をしたいという想いからである。
秋山郷は、牧之が旅した180年前と全く変わらぬ魅力で満ちている。それは、私には奇跡に思える。 |
|
 |